振動刺激による情報伝達装置の開発と
白杖等の自律歩行誘導支援
株式会社エヌアンドエヌ

開発したサービスの概要
振動刺激による情報伝達(コミュニケーション)装置の開発と白杖等の自律歩行誘導支援
エヌアンドエヌでは以前より、振動符号技術の開発を進めており、3件の特許も取得している。そして、こうした技術によって「カメラで捉えた現況情報を複雑な振動符号に変換して人体に伝達することで、視聴覚障がいのある方(白杖を使用している方)などの自律歩行支援に活用する」製品を世に出すことを目指してきた。この製品は人の命に関わるものであるため、開発をいくつかのステップに区切り、振動子の検査機器開発、スポーツ用途、読書用途などから模索し順次進めているが、今回の支援期間内ではなかでも振動情報の検査評価装置に重点を置き開発。さらに、今後の発展の可能性を見出した。
開発したサービスの紹介
振動コミュニケーションに不可欠な「振動」の評価装置を開発
人間の情報取得は視覚と聴覚が主であるが、「触覚を補助情報として取り入れた複合した取得と判断した方がよいのではないか?触覚が使えれば、障がいの有る無しに関わらず情報伝達方法の変革を興せるようになり、社会の新しいニーズが生まれるのではないか」という考えから、音声伝達コミュニケーションと同等かそれ以上のスピードで情報を伝えられる振動伝達装置の開発を行っている。今回開発した「振動評価装置NVX1001」は、符号語としての振動の制作装置であり、これまでの1/4〜1/5の伝達速度で振動情報を作ることができる。また、振動伝達装置に不可欠な「振動子」という部品の評価もできる。今後の「白杖等の自律歩行誘導支援」開発の土台となる装置といえる。
振動刺激を活用する際の触覚情報を創成・生成・規定する
「振動評価装置NVX1001」
「振動評価装置NVX1001」は振動子の検査や評価以外にも用途がある。振動発信の生成に必要な各種パラメーターや振動情報を意味想起させる振動制御では、これまでは手間がかかり経験や体験が必要だった振動創成作業を支援し、振動波形を数値化・視覚化・触覚知覚化する。そして取得情報の確認・評価・再現・記録などの有効性の実証評価を容易にする。机上で簡単に振動創作ができることも特徴だ。通常の点字リーダーを超える情報量や速度という課題に関する弁別・識別力を有する、振動符号語としての活用も期待できる。身体の狭小部位でも発信・識別容易な振動による符号語を700〜800種類程度まで拡大でき、最適な波形の創成支援にも役立つ。

障がい者スポーツ・短距離走レースのスタート合図に振動刺激を応用
今回の助成事業では、障がい者スポーツにおける短距離走のスタート合図に振動刺激を応用した開発も進行している。レースの際に短距離走選手が腕に振動子を装着し、スタートの合図として電気信号が送られると、皮下の振動刺激受容器が振動を感知する。このシステムには最低でも4種類の振動表現が必要だが、そのうち1つはフライングなどの緊急停止用で、わずか0.7秒程の受信時間で確実に伝わる振動を出さねばならないといった課題もある。現在は東京都障害者スポーツ協会に実証実験の協力を依頼し、実用化に向けて開発が進行している。
サービス開発のきっかけ
進歩した技術は「視覚障がいのある方の支援に活用」できる
車の運転中、込み入った道でカーナビが間に合わず曲がり角を通り過ぎてしまった、という経験をした人も少なくないだろう。これは情報処理・伝達のスピードの問題だ。「歩行者にとってはこのタイムラグは大問題。例えば鉄道駅のホームでの転落を防ぐには、“止まりなさい”という指示をホームの端から3歩手前で出す必要があります。さらにその前に画像処理をして情報を素早く提供しなければならず、なかなか実現できませんでした。しかし近年は技術が進み、駅のホームのエッジ検出などの解析ソフトの進歩や、何を検出するのが合理的かなど、考え方の進化が進んだことから白杖を持つ方のため使えるのではないか?と考えました」
開発期間中の振り返り
拙速なシステム開発よりも、装置の土台となる振動子の評価装置を
「当社では10年以上前から、社会の新しいニーズの可能性として振動刺激による情報伝達方法のアイデアはありました」と永瀬会長は言う。振動刺激による点字リーダーなど、すでに独自の開発を進めており、「白杖支援システムを作るだけ」ならば難しいことはなく、現行品より高性能なシステムを作る自信はある。ところ、このシステムの根幹である振動子に問題が見つかった。振動子は人工現実感や乗用車にも使われ、大量生産で安価に流通しているが、世界的に半導体不足とともに大量の粗悪品が出回ったのだ。「振動情報伝達機器に振動子は不可欠。拙速にシステム開発を進めるよりも、まずは振動子の評価装置の開発を目指しました」。
使用シーンを模索し、「障がい者スポーツ」という新たな道が拓けた
視覚障がいがある方が使うシステムは、医療機器と同様の信頼性が必要だ。そこで最初の段階では、健常者が使うシーンを想定し、アウトドア系ナビの会社と協力を模索したが不調に。駅伝やマラソンの監督が選手に指示を出す際に使えないかとヒアリングしたが「符号を覚えられない」と断られた。短距離走でのスタートに、振動で数種類の合図を送れば、直感を含めて情報の意味が体感できる方法を考案した。これが障がい者スポーツという新たな用途展開の始まりとなった。また、スタートの合図は「音」では1レーンと8レーンで0,0数秒のズレが出るが、腕につけた振動子に合図を送ればズレは軽微。ここで障がい者スポーツという新たな展開が生まれた。
一緒に伴走したコーディネーターがいたから、着地点が定まった
同社は技術開発者を中心としたエンジニア集団であり、開発力は非常に高い。一方、新規事業の進行といった面では不安もあったため、公社コーディネータが経営面でのアドバイスや事業ステップの整理を行った。「分かれ道に差し掛かった時には方向性を決めて一緒に伴走してくれたおかげで、着地点が定まりました」(曽根社長)。
今回の着地点は当初計画の第一段階までとなったが、今後の展開が期待できる装置ができた。「展示会では、コミュニケーションの基礎研究に携わっている方に言われ、この開発が認められていることを実感できた」。
これからのビジョン
様々な分野に貢献できる可能性が見え、今後も開発を続けていく
「これからのビジョンといえば、社会貢献に尽きます」と永瀬会長はいう。曽根社長も「当社の基本は受注産業であり、今まで私たちは“社会に貢献している”という実感を持っていなかったのです。今回の開発では “白杖支援”をゴールに掲げましたが、そこから様々な方向への発展の可能性が見つかり、視覚障がいがある方だけではなく多様な分野へ貢献できるのではないかと思っています。全ての分野に隔たりなくチャレンジし続けていきます」とのこと。
スポーツ関係機関や大企業・大学などの協力も得られ、今後は開発が加速するだろう。「近い将来、国際的な障がい者スポーツ大会で当社が開発した製品が活躍する可能性は十分あると考えます。」。
会社情報
| 社名 | 株式会社エヌアンドエヌ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 永瀬 明男 代表取締役社長 曽根 雅人 |
| 所在地 | 東京都大田区大森西5丁目28-16 |
| 事業概要 | 1990年、光学機器部品製作会社として創設。精密部品加工のみならず、設計部門・精密測定部門等を積極的に取り入れ、設計から製品まで一貫したサービスを提供。社会のニーズに迅速・柔軟に対応すべく日々挑戦を続ける。 |
| 主な製品やサービス | * |
| URL |
https://www.n-and-n.co.jp/ |
代表者情報
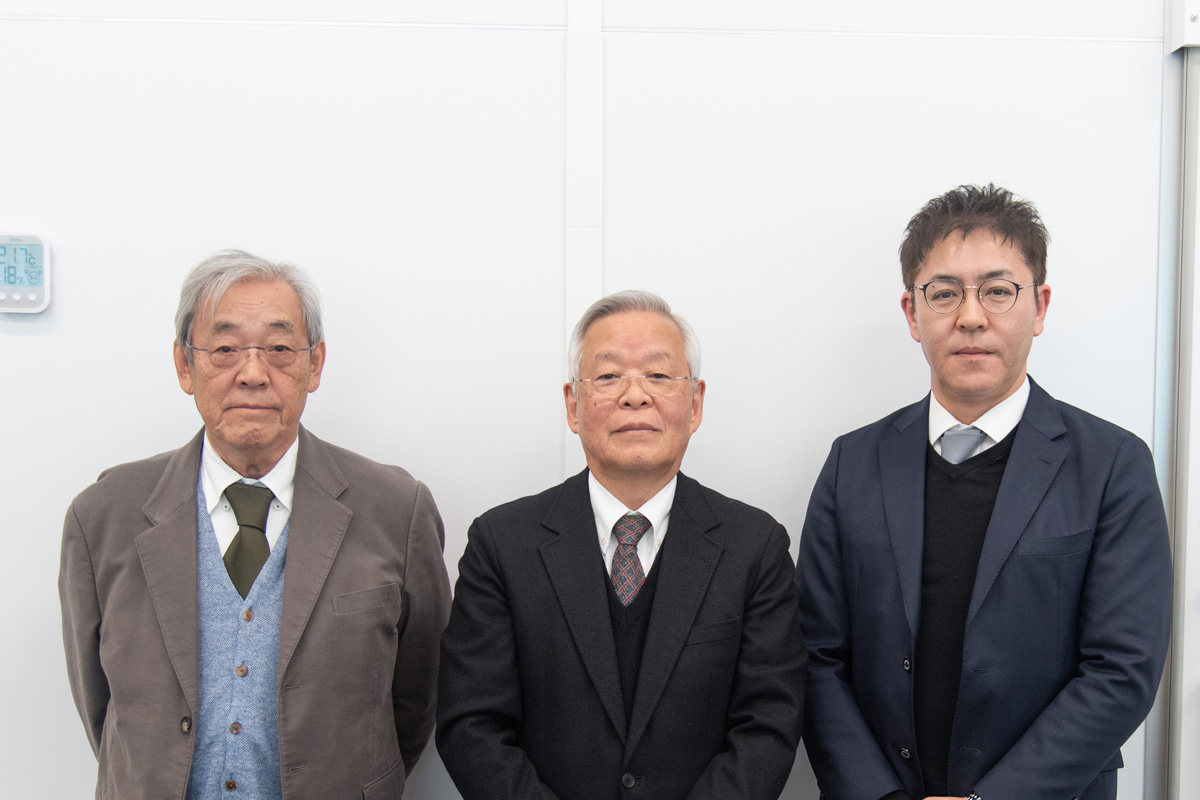
代表取締役会長 永瀬 明男
代表取締役社長 曽根 雅人