中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介
「全員経営」は社員の考える力を伸ばし、自立化を促す
株式会社国際協力データサービス
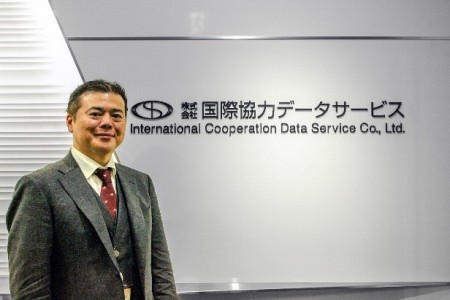
<会社概要>
設立:1990年
所在地:東京都千代田区麹町3-6-5 麹町GN安田ビル2階
資本金:5,180万円
従業員数:30名
事業紹介:
情報システムのコンサルティング、開発から保守運用までワンストップでのサービス提供を強みとするITソリューション企業。取引先は、独立行政法人国際協力機構(以下、JICA)を始め、国際協力関連団体や民間企業など多岐にわたる。
URL:https://www.icds.co.jp/
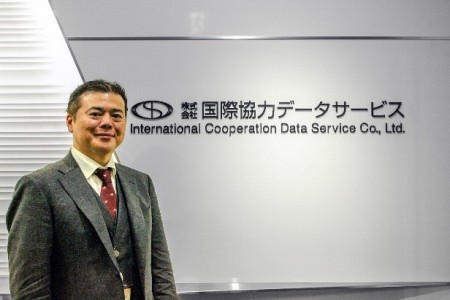
代表取締役の松島大介氏、ソリューション1課 課長の宮腰俊伸氏、ビジネス・クリエーション課 課長の吉山洋一氏にお話を伺いました
株式会社国際協力データサービスの設立は、1990年。JICAを主要顧客とするシステム系コンサルティング会社として、事業を開始した。
2018年には、一社員として働いていた松島氏が社長に就任。「第二の創業」を掲げて、新たな顧客層の開拓、新サービスの開発など積極的な事業展開を進め、現在ではITコンサルティングなど、上流工程支援へと事業の幅を広げている。
同時に、社員の人材育成や働きやすい環境整備にも注力し、2024年には第14回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞を受賞した。松島社長に受賞理由を尋ねると、「『社員を大切にして幸せにする』という信念のもと、様々な制度改革に取り組み、社員がその改革に応えてくれた結果だと思います。」と笑顔で答えてくれた。

「全員経営」の始まり
同社の人的資本経営の基盤となるのが、「全員経営」だ。「全員経営」とは、会社の方針や、ありたい姿について、社員全員が主体的に考える機会を設け、行動につなげるための仕組みである。
「社員の皆さんに『考える』という視点を持ってほしい。」この仕組みを取り入れた背景には、就任間もない頃の松島社長の強い思いがあった。
当時は、JICAからの委託事業により受注が安定していたことから、社員の多くが与えられた業務だけをこなす、受け身の姿勢だった。これからは競争が激しくなり、今の仕事がいつまでも続くとは限らない。今のままの姿勢では立ち行かなくなるとの危機感から、経営改革に着手することを社員に宣言した。「これからは『第二の創業』。自分も頑張るが、皆さんにも頑張ってほしい。」
同社の規模であれば、全員で改革に取り組んだ方が、一人ひとりの意識も高まり、効率も良いと考え、「全員経営」に取り組むことを決めた。
社員全員で考える、組織のありたい姿
「全員経営」の中心となったのが、全社員で参加して行われた経営品質の研修だ。「経営の設計図」と呼ばれる会社の指針に基づき、10年後、自分の部門では「どのようなお客様に、どのようなサービスを提供し、どのような関係を築いていきたいか」という、ありたい姿に向けた道筋(ロードマップ)を立て、それを実行するための計画(アクションプラン)を部門ごとに考える。
この新たな研修は、導入当初、社員からどう受け止められたのだろうか。
「初めは、みんな何をやっているのかわからなかったと思います。既存の事業以外には全く考えが進みませんでした。」松島社長は、戸惑いや反発のあった当初を振り返った。まずは考えることが大切だと、とにかく最後まで作りきってもらったという。それ以降、数年間は経営品質に関する研修を行い、その後は研修ではなく自分たちで見直しを繰り返してきた。
開始から6年が経ち、現場の指揮をとる宮腰課長は徐々に変化を感じていた。「1年で劇的に変わることはありません。ただ、毎年毎年繰り返すことで、漠然としていたり、飛躍しすぎていたりしたところが自然と落ち、我々の理念に近い部分が残ってきている気がします。」
加えて、目に見える成果も現れてきた。従来の組織にはない部門横断のプロジェクトチームが立ち上がり、自主的に活動が始まったのだ。例えば、同社のブランドを対外的に発信するブランディングチーム。事業開発を手掛ける吉山課長が社内で有志を募ると、複数の部門から計7名の社員が自ら手を挙げてくれた。サービスメニューの作成や、人事採用者向けの情報発信など、従来の業務を抱えながらも積極的に検討を進めてくれているという。販路拡大を目指す同社にとって、マーケティング、ブランティングは重要な取り組みであり、会社の目指す方向性を理解し、自立して考え、行動することを狙った「全員経営」の効果といえるだろう。
Will-Can-Must(WCM)シートで紐づく、部門のありたい姿と自分の役割
「全員経営」について社員の理解が進んできたのは、「WCMを導入したことも大きいと思います。」と宮腰課長。WCMは、自分のキャリアや役割を個人のやりたいこと(Will)、できること(Can)、会社から求められること(Must)の3つの要素から考えるフレームワーク。同社の場合は、前述のアクションプランから個人に求められることがMustとなり、それを自分のやりたいこと、スキルや能力と紐づけて考えることで、組織のありたい姿をより「自分事」として考え、行動につなげてもらうことができる。
2021年に一部の部門で試験的に開始し、2022年からは全社員に展開した。前述の研修同様、初めは「何を書いてよいかわからない」と戸惑う社員も少なくなかったことから、全社員の内容を公開し、まずは他の人のものも参考に書いてみることを促した。
また、WCMシートは書いて終わりではない。それに従い、あるべき姿の実現に向けて行動し続けることが大切になる。それを支えるのが、上司との面談だ。対話により目標達成を促し、モチベーション向上につなげていく。
同社でも3か月に1度、面談を設けているが、松島社長は上司からのフィードバックに問題を感じていたという。「ある時、30歳前後の社員から、『上司から評価されず、自己肯定感が上がらない』と言われました。人によっては、面談が振り返りや行動を促すフィードバックの場ではなく、単なる進捗管理になっているのではと思いました。」
そこで、面談の質を高めるために、評価者を対象としたコーチング研修を開始した。外部が定めた目標に向けた誘導型のコーチングではなく、社員自らのありたい姿に向けて支援する「思いやりのコーチング」を学んでいるという。受講者の一人である宮腰課長は、「気づきを促し、自立的な成長を支援するという意味で、当社に必要な研修です。外部からの期待に応えるのではなく、『何のために行うのか』『どのような自分でありたいのか』を大切にしながら対話を重ねることで、相手が気づいて、前向きになってくれます。私自身も前向きになり、気づきもあります。」と、実践した感想を語った。
一方、松島社長は、社員が自分のやりたいことに気づくことは、会社にとってリスクでもあると指摘する。「本当に自分がやりたいことが、当社ではできないこともあります。」実際に、そのような理由で辞めていった社員もいたが、この取り組みを止めることはなかった。「私にとっては賭けでもありますが、悶々と当社で働いてもらうよりも、他社でやりたいことを実現してもらった方がお互いにとって幸せです。」
時に、経営と相反する社員個人のありたい姿を尊重する姿勢は、縁ある人の幸せを掲げる同社のミッションと重なった。

ミッションに紐づく、働きやすさを追求した人事制度
同社のミッション「ICTで縁ある人を幸せに」は、2020年に松島社長が刷新したものだ。「当社の社員は人のためになりたいという思いが強いので、それにつながるものにしたいと思いました。」その後、当社では様々な人事制度が整備されているが、どの制度にもこのミッションが体現されている。
例えば、「積立休暇制度」。通常有給休暇は付与されて2年で失効するが、失効した休暇を最大20日まで積み立て、自分や家族のために利用することができる。これはかつて、病気の治療で欠勤せざるを得なかった社員の訴えを汲んだものだ。有給休暇は法定上、前年に年間労働日数の8割以上勤務しないと付与されないが、「積立休暇制度」があることで、前年の欠勤により有給休暇が出なかった場合でも、積み立てた日数分は有給休暇として活用したり、また制度を活用して欠勤が減った結果、有給休暇が付与される場合もある。
また、教育への投資も意欲的だ。社員のみならず、外部のパートナー技術者にも研修費用を補助し、専門技術の習得を支援している。結果として、パートナーの技術力向上に加え、信頼関係の強化にもつながっているという。
「全員経営」の視点を持つことで会社は飛躍する
「当社には、新しい価値を創造するための売れる仕組みと開発する仕組みが必要。今はそれをつくるための『成長痛』の時期です。」様々な取り組みで経営改革を進めてきたが、改革は未だ道半ばだという吉山課長。売れる仕組みについては、今年立ち上がったブランディングチームが担う。開発する仕組みについては、「開発系のプログラマーは、今後AIに変わっていく。私たちはシステムのより上流工程、つまりコンサルティング領域へとシフトする必要があります。」と松島社長は語る。そこで生きてくるのが、社員の「考える力」だ。「全員経営」を通してそれを培ってきたのは、この環境の変化を見込んでのことでもあった。
さらに、その先に海外展開を見据える。「国際という社名が付く以上、海外でのシステムコンサルティングなど人材やデータにかかわるビジネスを展開したい。」
「成長痛」の先にある、さらなる進化が期待される。
取材協力:山田 美鈴
※本記事は、2024年11月時点の情報です。

 採用情報
採用情報 よくあるご質問
よくあるご質問 サイトマップ
サイトマップ English
English
