中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介
人材育成の一丁目一番地は、経営者が社員の幸せを思う心にある
株式会社葵製作所

<会社概要>
- 設立:1977年
- 所在地:東京都八王子市石川町3216-7
- 資本金:1,000万円
- 従業員数:20名
-
事業紹介:
総合板金加工業として、各種大型筐体、フレーム、架台の板金加工から各種シャーシ、ケース類の精密板金加工まで幅広く対応。職人の技術にこだわりを持ち、難しい曲げ加工や薄物素材の微細な溶接加工など、製品に合わせた技術を磨いてきた。2023年にはインテリア雑貨ブランド「zuga」を立ち上げ、受託製造に留まらず自社企画製品の製造販売に進出している。 -
URL:https://www.aoi-ss.co.jp/

代表取締役の長谷川薫氏にお話を伺いました
株式会社葵製作所は、長谷川社長の父が1971年4月に創業した総合板金加工企業だ。1972年には八王子市に工場を開設。創業の頃は、放送局内で使用されるデスク型の放送設備機器といった大型設備の筐体(きょうたい)の取り扱いが多かったが、小型の精密板金加工も手掛けるなど、積極的に事業を拡大していった。
しかし、板金加工業界は2000年頃から新興国とのコスト競争など厳しい時代に突入。長谷川社長はもともと化粧品会社に就職していたが、父に請われて2001年に葵製作所に入社し、営業に奔走した。それから13年を経て、2014年に代表取締役に就任する。

模範的な製造業の裏に潜む課題
同社が創業後50年以上の歴史を重ねられたのは、その堅実な歩みによるところが大きい。社是として掲げられた「目計漸進(もくけいぜんしん)」は、会社も人も目標を定め計画を立てて慎重に前進することが大切だ、という父の考えを形にしたものだ。
また、適正な売価設定のために、創業後の早い時期から製造原価管理に取り組んできた。こうした管理の姿勢は原価に留まらない。これまで取り扱った製品の図面もきちんと保管し、すぐに取り出せる。各図面には作業の要点(コツ)が書き込まれ、他の職人でも再現可能となっているなど、工程管理が徹底されている。
このように、製造業としては模範的に見える同社だが、長谷川社長からは違った景色が見えていた。モノづくり企業として製造部の目線が強く、営業部は製造部のためにあるような位置付けだった。その製造部も就業中の私語は厳禁で、目の前の業務を集中して処理することが求められていた。会社としてはとにかく多くの仕事を取ってきてこなす、という雰囲気しかなく、意思疎通に欠け、社員はただ作業に追われているように映る。そんな状況に歯がゆさを感じていた。
社長として、会社として、あるべき姿とは
「社長になって、経営理念を示し共有することの必要性に気づき、改めてこの会社の存在意義について考えました。また、自分は技術ある父とは違う。そんな自分は何を成すべきか、とも自問しました」と長谷川社長は語る。その中で、「会社は社員一人ひとりの協力で支えられており、彼らにはぜひ仕事を楽しみ、幸せになってもらいたい。自分の成すべきことはそこにある」と悟った。
熟考の末、2018年1月に同社の経営理念「想いを共につくり、絆を育む」が制定された。そこには、社員を含む全てのステークホルダーとより良い関係性を構築したいという、長谷川社長の思想が込められ、日々の業務や人材育成など経営全般の拠り所となっている。
経営理念の社内浸透については、朝礼や会議で説いたり唱和したりといったことは敢えてせず、自身が理念を基準とした日々の振る舞いで範を示すよう意識しているという。例えば、メンバー間の意思疎通がうまくいかず、プロジェクトが難航しているような場合に、「そこに絆はあるの?」と投げかけて、社員の振り返りを促している。

社員のチャレンジ・成長を促すための「個人カルテ」
かつて父は、年2回の賞与支給時に各社員と面談を続けていた。長谷川社長もそれを引き継ぎ、現在は個々の社員とさらに深く向き合い、会社の方向性と社員のキャリアについて一緒に考える場として活用している。そこで話し合った内容を、継続的に記録したものが「個人カルテ」だ。カルテの1ページ目の上段には、会社がその社員に果たしてほしい「役割」と社員への「期待」が示されている。下段には社員自身がこうありたいと考える「目標」と、達成のための「実行」計画が記入され、定期的な面談の記録がその後に続く。
カルテの後半ページには社員の思考を促すように、「何の為に葵製作所が存在するのか」、「どんなゴール、目標が自分をワクワクさせ、幸せを感じられるか」といった問いかけが付されている。このカルテを通じた面談により、社員が自発的に考え意思表明するための環境ができた。今は年2回では足りず、年4回へと回数を増やして実施している。
中小製造業にとって従業員の多能工化は共通の課題だが、面談を重ねるうちに、自ら「全ての技術に対応できるようになりたい」と、高い目標を掲げる社員も現れ始めた。「自分で立てた目標をどんどん形にしていく社員もおり、今は少し控えめな社員をどう応援するか、花開かせるかにやりがいを感じている」と、長谷川社長もその効果に目を細める。
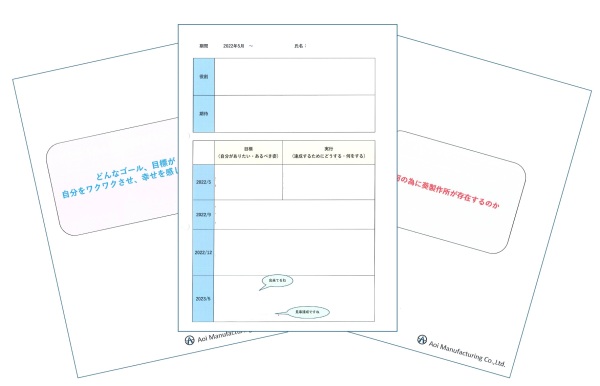
部門間の相互理解を促進する全社横断の「技術向上プロジェクト」
同社では、製造部を大型筐体グループと精密板金グループの2つに分け、分業制を敷いてきた。この体制は高い専門性が発揮できる一方で、コミュニケーション不足に偏る傾向がある。その改善策として取り組むこととした「技術向上プロジェクト」は、製造を中心とした学びの場であると同時に、製造部のグループ間、さらには営業部や管理部も含む全社的なコミュニケーション促進と一体感醸成を狙って長谷川社長が始めたものだ。年に1〜2回、就業時間中に全社員が集まって、各部門のリーダーが講師となり、自社の業務や技術について研修・ワークショップを行っている。
プロジェクトの回数を重ねることで製造部内では相互の業務理解が進み、各グループの繁閑に合わせた配置変更を社員自身が配慮できるようになり、生産性向上につながっている。営業部は製造現場の知識を得ることで、顧客への説得力が増した。なかには、CADの認定試験を受ける営業担当者や、溶接試験にチャレンジする管理部社員も現れるなど、自身のスキルの幅を広げようとする前向きな姿勢がみられるようになった。
現在このプロジェクトでは、2025年11月に開催される「八王子オープンファクトリー」の参加に向けて企画を練っている。これは八王子市等が主催するイベントで、住民がその地の工場や工房に実際に訪れて、ものづくりを身近に体験できる取り組みだ。同社では子供向けに、機械を使わずできる板金製品の企画アイデアを社員で出し合っている。子供たちの笑顔のために取り組む社員の思考の柔軟さは驚くほどだという。
「技術向上プロジェクト」を通じて自社の事業に対する理解を深め、会社への誇りにもつながる。「こんな素敵な取り組みはもうやめられない」と長谷川社長は声をはずませる。
コロナ禍での製品試作が生んだチャレンジする風土
コロナ禍では同社も受注が減少したが、長谷川社長は空いた作業時間で自分たちが作りたいものを作ってみよう、と製品試作を後押しした。そこに向かわせたのは「仕事を楽しんでほしい」という思いだ。これまでは顧客の依頼に基づいて製品を仕上げてきたが、自社製品を一から作り上げるのは勝手が違う。そのアイデアにニーズはあるのか、試作品の見た目はどうか、使用上の問題点はないか、など社内で自発的に意見が交わされた。できた製品を展示会で公開したところ評判が良く、「図画工作」のように真面目に楽しくという思いを込めて、「zuga」というブランドで正式に事業展開。量産されるプラスチック製品にはない金属の質感や堅牢性が評価され、今までとは異なる業態から、こんなものは作れないかと引き合いも来はじめている。
「以前は新たな案件に対して、ともすれば製造部が『ウチではできない』という反応をすることもありましたが、『zuga』の活動を通じて、顧客ニーズに応えようとチャレンジするようになりました」と、長谷川社長も社員の変化に手応えを感じている。

今後、更なる人材育成へ
同社は、「個人カルテ」や「技能向上プロジェクト」といった取り組みが外部から評価され、2024年3月には一般社団法人東京中小企業家同友会による「第2回人を生かす経営大賞」奨励賞を、同11月には東京都産業労働局による「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」奨励賞を受賞している。また、東京都産業労働局主催の2021年度東京ビジネスデザインアワードでは、社外のプロダクトデザイナーとのマッチングによりテーマ賞を受賞するなど、社外とのコラボレーションにも積極的だ。
長谷川社長に今後の目標を伺うと、「zuga」の販路開拓という事業目標に続けて、更なる人材育成に話題が及んだ。
「会社として、次世代のリーダーを育てていかないといけない、と考えています。まだ自分自身は元気ですが、早いうちから念頭に置いておく必要があると思います」
これからも社員の幸せを思い、彼らと向き合う
同社はコロナ禍を乗り越えて以降、業績は堅調に推移し、離職者も出ていない。また、2023年には20代の男女2名が入社し、着実にスキルアップしている。それは長谷川社長が日々の作業に追われているだけの社員を憂い、新たな経営理念を柱に社員の自主性向上や相互理解・関係性強化に取り組んだ賜物だろう。「当社もまだまだのところがありますが、おかしいと思うところは蓋をせず社員と向き合い、正しくあるよう心掛けたい」と長谷川社長。人材育成の一丁目一番地は、社員の幸せを思う心にあると示してくれた。
取材協力:北川 雅也
※本記事は、2025年7月時点の情報です。

 採用情報
採用情報 よくあるご質問
よくあるご質問 サイトマップ
サイトマップ English
English
